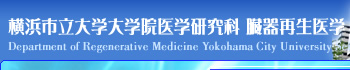 |
 |
 |
||
|
|
| 〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 TEL:045-787-2621 / FAX:045-787-8963 お問い合わせはこちら Copyright © 横浜市立大学大学院医学研究科 臓器再生医学 All Rights Reserved. |
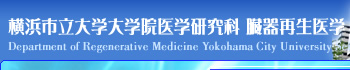 |
 |
 |
||
|
|
| 〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 TEL:045-787-2621 / FAX:045-787-8963 お問い合わせはこちら Copyright © 横浜市立大学大学院医学研究科 臓器再生医学 All Rights Reserved. |