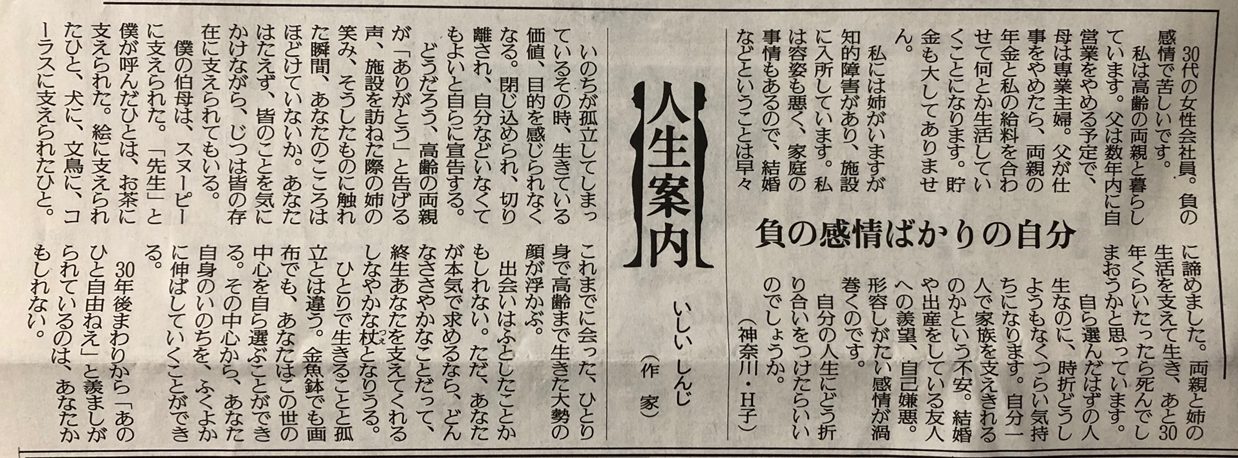まったくもって個人的な話で恐縮ですが、昨年12月に高校の同窓会がありました。卒後45年にして初めての同窓会で、同期卒業生400名のうち142名が参加し、大いに盛り上がりました。
ところで、高校生の時に聞いた授業の中で今でも憶えている話が一つだけあります。それは世界史の授業で、その時、若林靖太郎先生はモンゴル帝国の話をしてくれました。いつもの通り、黒板の下半分全体にチョークで板書し、一通りの説明が終わった後、先生が皆に質問したのです。
「モンゴル民族が、世界征服ともいえる大帝国を築けた理由は何か?」
私は、それはチンギスハンが偉かったからだよ、と思いました。直前までの先生の説明からもそれが妥当な答えのはずでした。しかし、先生の答えはこうでした。
「モンゴル人が、あぶみを発明したからです。」
意外でした。あぶみの発明が世界征服に繋がった。モンゴル帝国を築いた功績者はチンギスハンではなく、名もないモンゴル人(達)ということになります。意外だったけど、確かにそうなのかなー、とも思えました。あぶみによって馬の操縦性が向上し、騎馬民族の機動力・軍事力が格段に高まったと先生が説明してくれたからです。
大人になった今、国というレベルで物事を考える時、「国力≈科学技術力」という認識は、多くの人が共有していると思います。その意味で、若林先生の話は大人にとっては当然の内容かもしれません。けれど、あぶみという小道具の発明が歴史を変えたという話には、個人レベルの作業と国家の興亡を繋げるダイナミズムがあり、心躍るものがあります。同時に、国家のことを考える際においても、個人個人がそれぞれ固有の課題に向き合い続けることが、何よりも大事なんだと教えられる気がします。自分の研究テーマが些細なことのように思えても、どこまでもそれを追求していくことが大事なのだと。
若林先生のあぶみの話は長く私の記憶に残り、折に触れて思い出していました。そして、その出典が気になっておりました。実は、ネットで調べる限りでは、あぶみの発明は3~4世紀の中国らしく、若林先生の説明と符合しません。上記の同窓会に若林先生が出席して頂けるなら、そのことをお聞きする絶好の機会だと思っていました。しかし、若林先生は2021年に他界されており、先生にお会いすることは叶わないことを知りました。残念でしかたありません。
そんな中、同級生の一人からLINEが来ました。若林先生の想い出を語る会を持ちたいというのです。若林先生のファンが多いことを知りました。来週の日曜日、皆と一緒にお墓参りをし、思い出を共有したいと思います。