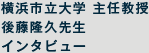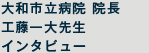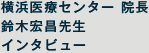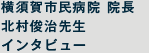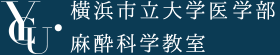時代の渦に飲み込まれた半生。
麻酔科医には病院を変える力がある
(独)国立病院機構横浜医療センター 院長
鈴木 宏昌

獣医を目指したものの、医師となり麻酔科への道へ
私は四男で、一番下に年が離れて生まれたんです。両親が、どうしても女の子が欲しいということで産んだそうなんですが、結局男だったという(笑)。勉強はしませんでした。親から勉強しろと一度も言われたことありませんし、通信簿も親に見せないで全部自分でハンコを押していました(笑)。親も四男なんで「好きに生きてて」って感じなんですよ(笑)。逆に兄貴たちは口うるさく、私のことをよく見ていましたね。
父親は4人男がいるなら1人は医者にしたいと思っていたらしいんです。でも私は工学系や科学系が好きだったので、最初は車の技術者になりたかったんですよ。それから高校生になり、動物好きが高じて獣医になろうと思いました。ですが、結局浪人しちゃったんで、なぜか医者になってしまいました(笑)。
医学生のときも、当初は外科か整形外科になろうと思っていたんですけど、なぜか麻酔科を選んでしまいましたね(笑)。麻酔科は今これだけメジャーになりましたが、我々が学生の頃は将来の専攻科として一般的ではなかったです。私は1985年(昭和60年)卒業ですが、横浜市大で麻酔科ができたのは1970年(昭和45年)。ですから、一番新しい診療科だったんですよね。教授もまだ2代目教授でしたし。
私は四男という立場で生きてきて、控えめな性格だったからか、当時は外科医のように自分の実力でダイレクトに結果が出てしまう仕事に今一つ自信がなかった。一方で、麻酔科っていうのは治療をする科ではなく、技術職ですから面白いし、自分で完結できるっていう仕事が比較的私には合っていました。また、当時の沼田克雄教授が非常にいい先生だったことも理由の一つですね。昭和天皇の麻酔をかけた先生なんですよ。技術的にも素晴らしかったし、適正な考え方をする、温和でいい先生だったんですよね。こういう人についていけたらいいな、と思って、最終的に麻酔科を選びました。
いかに時代とチャンスの波に乗れるかが、人生を左右する

私は四男なので順応性が高いのか、時代の渦にぐるぐると巻き込まれながらなんとか生きてきました。また今、院長になったらコロナウイルスに翻弄されて(笑)。そういう運命にあるんでしょうね。
私は医師として複数回のエポックメーキングな出来事に遭遇し、その影響で医療界の大きな変化を経験してきました。特に最も大きな影響を受けたのは、1999年(平成11年)1月11日に大学で起こった「患者取り違え事故」ですね。当時私は全く別の病院にいて、すでに中堅の麻酔科医になっていましたが、大変ショックを受けました。さらにこの問題が解決する前に、当時「医局つぶし」といわれた「臨床研修必修化」(2004年・平成16年)が迫ってきました。当時赴任した山田芳嗣新教授から、「患者取り違え事故」と「臨床研修必修化」の2つの問題に対処できる人間を医局内で探せ、という指示が発せられ、なぜか私に白羽の矢が立ったんです。それで大学に戻って医局長になりました。人生って数奇ですよね(笑)。私がこの立場にいるっていうのは実力ではなく、時代の流れに自ら乗ったのかもしれない(笑)。ちょうどそういう時代の潮目に立ち会ったという感じですね。その後、関連病院の麻酔科部長になりましたが、医局長も兼任、結局足かけ5年医局長をやりました。医局初の大学病院以外に勤務する医局長ですね。
先ほども話しましたが、私は最初獣医を目指していて、東京農工大学に進学したんです。でも獣医学部に進めず、人生の方向性が変わってしまいました。でもちょうどその年は、共通一次試験の初年だったんです。だいたい最初は簡単(だろう)と思い、受けてみることにしました(笑)。こういったシステムが変わるとき、エポックメーキングなところでいかにうまく行動するかって、大事なんだろうと思うんですよね。チャンスの波に乗れるものなら乗ってみようかなという感じ。だから私は時代の波に乗ったんですかね。
なぜ私が院長なったのか、自分でもよくわかりません。私が若いころに見た院長や上司の人たちは、皆さん強烈な個性を感じる方々で、大企業のトップも強面で迫力やカリスマ性のある人がなる、というイメージでした。しかし、バブルが崩壊したとき、ある都市銀行のトップに就いた方がすごく温和な方で、それを見て「時代が変わったな」という感じがしたんです。そしてもしかすると、私もその時代の波に乗れるかもしれないな、と思いました。昔とは違って、これからは比較的温和で静かな人がトップになるのかな、って。やはり時代って変わるときが来るんですよ。でももう私の世代はもうおしまいなんで、次の世代に託そうと思います(笑)。明らかに今、コロナで時代が変わる。まさにエポックメーキングがまた来たかという感じです。本当に、最後の最後まで翻弄されていますね (笑)。
独学で磨いたゴルフの腕。幼いころにプロを目指したかった!?

趣味といえば、最近はゴルフしかしてないですね。一番多いときは年間60回くらい行きましたが、最近は年間30~40回くらいかな。研修医の頃から続けています。学生時代は野球部だったんですよ。でも野球が終わっちゃって、同級生が「部活終わっちゃったしゴルフの練習でも行こうか」っていうので始めたんです。
そもそもゴルフには子どもの頃から興味があって、小学校5年生のときに親に「ゴルフやらせてくれ」って言ったんですよ。1960年代の後半はゴルフが大変流行っていて、父親自身も趣味でプレーしていたんです。ところが「馬鹿!」って怒られて(笑)。父も母も大正生まれで、父親は普通のサラリーマンですが、「遊びを仕事にするものじゃない」って却下されちゃいました。そのときはテレビでゴルフ中継が始まったばっかりだったので、プロになりたいって思ったんですけどね。
ゴルフを始めて、最初だけプロに習いました。でも人に教わるのが好きじゃないので、結局独学です。だからうまくならないんですけどね(笑)。
実力社会で生きるために。病院の発展のカギは「麻酔科医の活躍」
2007年(平成19年)から勤務した相模原協同病院が、私の考え方を変えた病院なんです。かつての優良病院は、臨床研修必須化の影響で年間10億円以上の赤字が出る病院になっていました。これを1年で黒字病院に変えました。麻酔科医3人(1名は新人)で赴任しましたが、たった3人では何もできないな、と考えていました。そこで、手術室を徹底的に変えることに特化しました。きれいに掃除し、薬品や道具を使いやすいよう整理整頓をしたんです。急性期病院の収益は手術なんですよ。手術の件数が増えないとやっていけない。だから、麻酔科医として、外科医や看護師が使いやすくみんなが過ごしやすい手術室へと変え、結果的に病院全体が良くなったんです。麻酔科医は、手術室の細かいところに目が効きます。つまり、麻酔科医が適切に働けば、病院がどんどん良くなるんですよ。しかも外科系だけじゃなく、内科系やコメディカルまでそれは伝わるんですよね。そうすると、自然と病院自体がうまく運営できる雰囲気ができてくる。非常に面白い経験でした。手術室は中央部門。麻酔科医は中央部門を管理しています。中央部門がきちっと動くと、病院というのはうまく動くっていうことを実感しました。そういう麻酔科医の役割っていうのが、病院の管理者としても向いているんだと思います。
人間関係も同じですが、いかにパートナーに信頼されるかというのが非常に大事ですね。麻酔科医のパートナーは外科系医師です。この人たちは、信頼できる麻酔科医かどうかを瞬時に見分けます。その信頼を失うと、非常につらいことになります。ただでさえ手術室ではトラブルが起こりやすいですし、それを解決しないと命に関わりますから。信頼を得るには、適切な知識と経験、そして仕事に臨む対応力なんでしょうね。医者っていうのは専門家軍団。その人たちを邪険に扱うわけにはいかないです。それぞれのスペシャリティを尊重して、こちらも言うべきことは言う。そういうことができる人が好まれます、私みたいに(笑)。もちろん、リーダーシップや業務にあたる姿勢とかっていうのは後で勉強することができます。アメリカなんかではそういった研究がされています。でも多少は生まれ持ったものもあると思いますけどね(笑)。
これからの人口減少に伴い、相対的な医師過剰となる可能性があります。今の世代の医師たちは、上の世代のポストの空きを待っていても出てこないでしょう。もう自分の実力で上がっていかなければ厳しいと思っています。少なくとも医師は差別化されるので、能力を上げることが必要でしょう。英語も勉強するといいと思います。世界中の医者が英語の教科書で勉強をしています。中学生~高1レベルの英語力と専門用語の単語さえわかれば、世界中で医者ができますから。あとはコミュニケーション能力が必要ですかね。信頼につながっていくと思います。皆さん頑張りましょう!
鈴木 宏昌(すずき・ひろまさ)
横浜市立大学卒。2003年(平成15年)から4年6か月、横浜市立大学麻酔科医局長。この間、済生会横浜市南部病院、藤沢湘南台病院、相模原協同病院で勤務。2009年(平成21年)新築前年の国立病院機構 横浜医療センターに赴任、手術部長、副院長を経て2019年(平成31年)4月より院長に就任。2017~19年(平成29~令和元年)(公社)日本麻酔科学会常務理事、横浜市立大学医学部臨床教授。
写真:鈴木智哉 取材・文:関由佳