
 参画機関
参画機関
データとテクノロジーが変える「働き方」のリデザイン
「子育て世代の時間貧困解消と男女共同参画を目指した産学官共創ラボ」の参画機関のひとつである株式会社NTTデータのソーシャルデザイン推進室は、生活者視点で社会課題に向き合い、企業・業界の垣根を越えて新しい社会をデザインしていくことに取り組んでいます。
「次世代にあう新しい働き方」をテーマに、出産を機とする女性の正規雇用比率降下の解消により男女共同参画社会、女性に限らず全ての働く人が多様に活躍できる社会の実現を目指して、働き方変革先進企業である、コニカミノルタジャパン株式会社、株式会社NTTデータグループ両企業の人事担当、そして医療やデータサイエンス分野のアカデミアトップランナーである横浜市立大学との対談を行い、ここで、「社員一人ひとりに寄り添った働き方には、データやテクノロジーが鍵となる」という新たなデザインへのヒントを得ることができました。
対談の様子を株式会社NTTデータからご報告いただきます。
1.「働き方」リデザインに向けた障壁と課題
 YCU黒木
YCU黒木
「新しい働き方」を推進していく上で感じている障壁や課題はありますか?
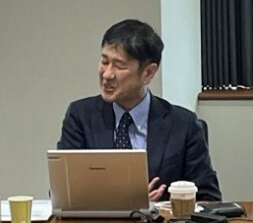
 コニカ伊崎
コニカ伊崎
我々は「いつでも、どこでも、だれでも働ける環境づくり」に向け「いいじかん設計」として多くの企業に先駆けて働き方改革を実践してきました。しかし、我々情報機器装置を扱う専門商社として、お客様次第で業務場所・業務遂行が左右される部分もあり、まだまだ現場に理解を得るのが難しいところがあります。 働きやすさばかりに注力すると成長意欲が低下する傾向も見られるため、働きやすさと働きがいのバランスを取ることがとても重要です。また、リモートワーク併用の中、社員同士のリアルなつながりをどう維持するかについても今後の課題です。
 コニカ高須
コニカ高須
海外現法は、働き方の地域差が大きいことも課題の一つです。 進んでいるイギリス現法は、オフィス無し完全にリモートですが、コミュニケーションを補う施策を多く立てています。例えば、毎週オンラインでタウンホールを行い、経営層の考えの発信や施策の進捗報告に加え、社員からその場で質問を受け、答えられない内容は翌週に回答をしています。あるいは、社員間ティールーレットと称してルーレットで当たった人同士でティータイムを楽しむという施策を進められています。
 NTTD土佐
NTTD土佐
社員間ティールーレット、面白そうですね。NTTデータでは多様な働き方の実現手段としてリモートとリアルのハイブリッドを基本にしています。リモートワークが進む中、新入社員や若手社員がリモートだけで本当に成長できるか、また組織力や社員エンゲージメントをどう維持、向上させるかは大きな課題です。
2.「女性活躍推進」における変遷
 YCU黒木
YCU黒木
> 少し視点を変えて、女性活躍推進について教えてください。冒頭で出産を機とする女性の正規雇用比率の降下(通称L字カーブ)について触れましたが、これまで「女性の活躍とキャリア選択、そのための組織風土づくり」という観点で進められてきた具体的な取り組みや、そこから見えた課題はどんなものでしょうか。
 コニカ伊崎
コニカ伊崎
女性の活躍推進については、当社ではリモートワーク環境の整備、育休から復職する社員へのキャリア相談などを実施して、女性が働きやすい環境を整えています。 しかし、もっと多くの女性が意思決定の場に関与することが必要であり、経営層や幹部、会社全体に多様性認知をもっと促進する必要があります。 また、管理職を目指す意欲が男女共に低いことも大きな課題です。専門性を追求するキャリアパスと管理職を目指すキャリアパスの両方に選択があることで、本人の意欲的なキャリアを指向していただくことが必要です。
 コニカ小室
コニカ小室
意思決定層が多様でないことが課題です。例えば、以前経営執行会議で出席した女性が私一人ということもありました。多様にするため、管理職に選ばれる側というマインドから、自分から管理職になるということ選ぶ側へのマインドチェンジする必要があります。
 NTTD豊島
NTTD豊島
女性活躍推進はジェンダーだけでなく、働き方や育児との両立、男性の育児参加にも大きく関連しています。 当初は女性が辞めないように制度や環境を整えることに重きを置いていました。現在は、より多様なキャリアパスを提供し、女性の能力を発揮できるような環境づくりが大切だと感じています。 女性の管理職志向は20代中盤から30代中盤で減少する傾向があり、ライフイベントや出産・育児が影響しているためと考えられます。 管理職へのチャレンジ意欲を高めるための1つの方策として、例えばメンバーを動かしながら自身でプロジェクトへの関与を裁量で決められるといった、管理職の方がむしろ働き方の融通が利かせ易い、楽しくやりがいもあることを人事としても伝えていきたいです。

 NTTD土佐
NTTD土佐
NTTグループ全体でも女性役員を増やすことを目標にしており、ふさわしい人材を任用することが重要だと感じています。そのためには役員自体多様性豊かな人材である必要がありますが、現在の女性役員比率を見ても未だ道半ばだと言わざるを得ません。役員の母数となる、マネジメント志向する社員の意欲をどう引き出すかが課題です。 単に、給与といった直接的施策だけでは管理職を増やすことには繋がらず、持続的イノベーションの実現や自己成長には、意識変革を進めることが本当に必要なんだと実感しています。そのため我々は、従来のマネージャーを目指すキャリアパスに加え、専門性を高め、突き詰めることで同等の処遇を得られる選択できるキャリアパスも整備しています。
3.データやテクノロジーの活用により「働き方」はどう変えられる?
 YCU黒木
YCU黒木
ありがとうございます。これまでの取り組みの様子がよくわかりました。IT技術の発展により、データやテクノロジーはあらゆる業界で活用されていますが、「働き方」における可能性についてはどのように考えていますか?
 コニカ伊崎
コニカ伊崎
「働き方」で活用できるデータのメインはやはり個人の業績評価になります。一方で、最適な人材配置の検討に向けては個人の嗜好や適性検査のデータなども活用したいところですが、人は環境や状況によって変わるため、分析が本当に難しいです。 ただし、データやテクノロジーを駆使し論議素材として扱うことで、社員に寄り添った制度設計や社員個別のキャリアプラン・ライフプランが提供できると考えており、大きな可能性を感じています。
 NTTD土佐
NTTD土佐
我々はIT業界の企業ということもあり、人事部門としてもデータやテクノロジーの利活用に敏感でありたいと思っています。例えば、AIを業務プロセスに組み込むことで業務の効率化を図り、社員がより高付加価値な業務に集中できるようにするような施策や、社員に関するデータを統合・分析・活用して、組織運営や人材配置における洞察を得ることにもトライできるのではないかと考えています。当社では、毎年社員エンゲージメント調査を実施していますので、これも活用して社員の満足度や組織の健康状態の理解、改善策の実現にもつなげていきたいです。
 コニカ小室
コニカ小室
一方で、高度なテクノロジーとデータ分析だけがあっても、リテラシーが足りていないと制度設計や施策へ反映できないという課題もあります。分析結果から導かれた改善施策の導入には、社員の心情に寄り添うことやデータを利活用する人の意識、スキルの底上げも必要です。この両輪を成立させることで有効な利活用ができると考えます。
4.「働き方」のリデザインに向けた考察
 コニカ伊崎
コニカ伊崎
社員のライフ面での支援として、様々なプランを整備し、社員に提案しています。 しかし、あまり多くの支援を提供し過ぎることは、社員が何をしたいか、社員自身がどんなキャリアを描きたいかの意欲を減衰する場合もあります。 会社が多彩なプランを提案することに限らず、自分でキャリア全体を考え自らが行動できることを促すべきと考えています。
 NTTD土佐
NTTD土佐
既に多くの制度が整っています。更に新しい制度を導入することよりも、今ある制度を社員自身が知らなかったり、あるいは活用できていなかったりすることを防ぐため、継続的な利用促進が必要です。 ライフイベントを迎えた時に、会社や上長が制度を理解し適切なアドバイスをできるようにしていきたいです。

 YCU黒木
YCU黒木
今回のディスカッションで特に印象に残ったのは、社員それぞれが自己決定できる環境を作ることの重要性です。 しかし、学生や若い世代を見ていると、男女問わず管理職を目指す意欲が低い現状が課題だと思います。これらは、経済状況の停滞もあり、人々の思考が近視眼的になっているため、将来に向けた楽しい人生を想像しにくいのであろうと推察しています。 さらに、特に女性の場合、国際レベルでみても管理職になろうとした際に仕事と生活両面の障壁がまだ多く、管理職制度やその役割を含めてどう解決するかが両社共通の課題です。 これを打破していくため、人事システムの改善、すべての職層における多様性の向上、仕事だけではなく生活との2軸に基づく評価の必要性などが挙げられると考えます。 そのために重要になるのはやはりデータとテクノロジーの活用です。社内外にあるデータを繋げて更に活用し、過去からの慣習で意思決定を行う偏りを避け、多くのエビデンスを用いて意思決定や人材教育、給与や働く環境面に関わる制度改革を行っていくことが必要だと考えます。データとテクノロジーの活用が促進されることで、全ての働く人が多様に活躍できる社会の実現を期待できます。
5.終わりに
社員一人ひとりに寄り添った多様な働き方の実現には、それらに応じた人を活かす新しい制度や文化づくりが必要です。そのために「仕事と生活」の状態を両側面から支えるための新たな客観視できる価値の基準と、人や情報等を「つなぐ」ことによって更に豊かなワークライフが追及できる仕掛けが必要ではないかと考えます。 新しい社会に添った基準づくりについて、株式会社NTTデータと横浜市立大学は共同研究をしながら、「子育て世代の時間貧困解消と男女共同参画を目指した産学官共創ラボ」でもともに活動しています。「つなぐ」役割を果たしながら、社会課題解決ビジネスの創出をより一層推進していきます。
 関連ページ
関連ページ
NTTデータがめざす社会課題解決 | NTTデータ(https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/socialdesign/)
コニカミノルタジャパン働き方改革の歩み | コニカミノルタ(https://www.konicaminolta.jp/business/solution/ejikan/about/index.html)
「新しい働き方」を推進していく上で感じている障壁や課題はありますか?
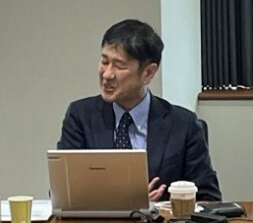
我々は「いつでも、どこでも、だれでも働ける環境づくり」に向け「いいじかん設計」として多くの企業に先駆けて働き方改革を実践してきました。しかし、我々情報機器装置を扱う専門商社として、お客様次第で業務場所・業務遂行が左右される部分もあり、まだまだ現場に理解を得るのが難しいところがあります。 働きやすさばかりに注力すると成長意欲が低下する傾向も見られるため、働きやすさと働きがいのバランスを取ることがとても重要です。また、リモートワーク併用の中、社員同士のリアルなつながりをどう維持するかについても今後の課題です。
海外現法は、働き方の地域差が大きいことも課題の一つです。 進んでいるイギリス現法は、オフィス無し完全にリモートですが、コミュニケーションを補う施策を多く立てています。例えば、毎週オンラインでタウンホールを行い、経営層の考えの発信や施策の進捗報告に加え、社員からその場で質問を受け、答えられない内容は翌週に回答をしています。あるいは、社員間ティールーレットと称してルーレットで当たった人同士でティータイムを楽しむという施策を進められています。
社員間ティールーレット、面白そうですね。NTTデータでは多様な働き方の実現手段としてリモートとリアルのハイブリッドを基本にしています。リモートワークが進む中、新入社員や若手社員がリモートだけで本当に成長できるか、また組織力や社員エンゲージメントをどう維持、向上させるかは大きな課題です。
2.「女性活躍推進」における変遷
> 少し視点を変えて、女性活躍推進について教えてください。冒頭で出産を機とする女性の正規雇用比率の降下(通称L字カーブ)について触れましたが、これまで「女性の活躍とキャリア選択、そのための組織風土づくり」という観点で進められてきた具体的な取り組みや、そこから見えた課題はどんなものでしょうか。
女性の活躍推進については、当社ではリモートワーク環境の整備、育休から復職する社員へのキャリア相談などを実施して、女性が働きやすい環境を整えています。 しかし、もっと多くの女性が意思決定の場に関与することが必要であり、経営層や幹部、会社全体に多様性認知をもっと促進する必要があります。 また、管理職を目指す意欲が男女共に低いことも大きな課題です。専門性を追求するキャリアパスと管理職を目指すキャリアパスの両方に選択があることで、本人の意欲的なキャリアを指向していただくことが必要です。
意思決定層が多様でないことが課題です。例えば、以前経営執行会議で出席した女性が私一人ということもありました。多様にするため、管理職に選ばれる側というマインドから、自分から管理職になるということ選ぶ側へのマインドチェンジする必要があります。
女性活躍推進はジェンダーだけでなく、働き方や育児との両立、男性の育児参加にも大きく関連しています。 当初は女性が辞めないように制度や環境を整えることに重きを置いていました。現在は、より多様なキャリアパスを提供し、女性の能力を発揮できるような環境づくりが大切だと感じています。 女性の管理職志向は20代中盤から30代中盤で減少する傾向があり、ライフイベントや出産・育児が影響しているためと考えられます。 管理職へのチャレンジ意欲を高めるための1つの方策として、例えばメンバーを動かしながら自身でプロジェクトへの関与を裁量で決められるといった、管理職の方がむしろ働き方の融通が利かせ易い、楽しくやりがいもあることを人事としても伝えていきたいです。

NTTグループ全体でも女性役員を増やすことを目標にしており、ふさわしい人材を任用することが重要だと感じています。そのためには役員自体多様性豊かな人材である必要がありますが、現在の女性役員比率を見ても未だ道半ばだと言わざるを得ません。役員の母数となる、マネジメント志向する社員の意欲をどう引き出すかが課題です。 単に、給与といった直接的施策だけでは管理職を増やすことには繋がらず、持続的イノベーションの実現や自己成長には、意識変革を進めることが本当に必要なんだと実感しています。そのため我々は、従来のマネージャーを目指すキャリアパスに加え、専門性を高め、突き詰めることで同等の処遇を得られる選択できるキャリアパスも整備しています。
3.データやテクノロジーの活用により「働き方」はどう変えられる?
ありがとうございます。これまでの取り組みの様子がよくわかりました。IT技術の発展により、データやテクノロジーはあらゆる業界で活用されていますが、「働き方」における可能性についてはどのように考えていますか?
「働き方」で活用できるデータのメインはやはり個人の業績評価になります。一方で、最適な人材配置の検討に向けては個人の嗜好や適性検査のデータなども活用したいところですが、人は環境や状況によって変わるため、分析が本当に難しいです。 ただし、データやテクノロジーを駆使し論議素材として扱うことで、社員に寄り添った制度設計や社員個別のキャリアプラン・ライフプランが提供できると考えており、大きな可能性を感じています。
我々はIT業界の企業ということもあり、人事部門としてもデータやテクノロジーの利活用に敏感でありたいと思っています。例えば、AIを業務プロセスに組み込むことで業務の効率化を図り、社員がより高付加価値な業務に集中できるようにするような施策や、社員に関するデータを統合・分析・活用して、組織運営や人材配置における洞察を得ることにもトライできるのではないかと考えています。当社では、毎年社員エンゲージメント調査を実施していますので、これも活用して社員の満足度や組織の健康状態の理解、改善策の実現にもつなげていきたいです。
一方で、高度なテクノロジーとデータ分析だけがあっても、リテラシーが足りていないと制度設計や施策へ反映できないという課題もあります。分析結果から導かれた改善施策の導入には、社員の心情に寄り添うことやデータを利活用する人の意識、スキルの底上げも必要です。この両輪を成立させることで有効な利活用ができると考えます。
4.「働き方」のリデザインに向けた考察
社員のライフ面での支援として、様々なプランを整備し、社員に提案しています。 しかし、あまり多くの支援を提供し過ぎることは、社員が何をしたいか、社員自身がどんなキャリアを描きたいかの意欲を減衰する場合もあります。 会社が多彩なプランを提案することに限らず、自分でキャリア全体を考え自らが行動できることを促すべきと考えています。
既に多くの制度が整っています。更に新しい制度を導入することよりも、今ある制度を社員自身が知らなかったり、あるいは活用できていなかったりすることを防ぐため、継続的な利用促進が必要です。 ライフイベントを迎えた時に、会社や上長が制度を理解し適切なアドバイスをできるようにしていきたいです。

今回のディスカッションで特に印象に残ったのは、社員それぞれが自己決定できる環境を作ることの重要性です。 しかし、学生や若い世代を見ていると、男女問わず管理職を目指す意欲が低い現状が課題だと思います。これらは、経済状況の停滞もあり、人々の思考が近視眼的になっているため、将来に向けた楽しい人生を想像しにくいのであろうと推察しています。 さらに、特に女性の場合、国際レベルでみても管理職になろうとした際に仕事と生活両面の障壁がまだ多く、管理職制度やその役割を含めてどう解決するかが両社共通の課題です。 これを打破していくため、人事システムの改善、すべての職層における多様性の向上、仕事だけではなく生活との2軸に基づく評価の必要性などが挙げられると考えます。 そのために重要になるのはやはりデータとテクノロジーの活用です。社内外にあるデータを繋げて更に活用し、過去からの慣習で意思決定を行う偏りを避け、多くのエビデンスを用いて意思決定や人材教育、給与や働く環境面に関わる制度改革を行っていくことが必要だと考えます。データとテクノロジーの活用が促進されることで、全ての働く人が多様に活躍できる社会の実現を期待できます。
5.終わりに
社員一人ひとりに寄り添った多様な働き方の実現には、それらに応じた人を活かす新しい制度や文化づくりが必要です。そのために「仕事と生活」の状態を両側面から支えるための新たな客観視できる価値の基準と、人や情報等を「つなぐ」ことによって更に豊かなワークライフが追及できる仕掛けが必要ではないかと考えます。 新しい社会に添った基準づくりについて、株式会社NTTデータと横浜市立大学は共同研究をしながら、「子育て世代の時間貧困解消と男女共同参画を目指した産学官共創ラボ」でもともに活動しています。「つなぐ」役割を果たしながら、社会課題解決ビジネスの創出をより一層推進していきます。
NTTデータがめざす社会課題解決 | NTTデータ(https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/socialdesign/)
コニカミノルタジャパン働き方改革の歩み | コニカミノルタ(https://www.konicaminolta.jp/business/solution/ejikan/about/index.html)
