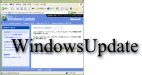 修正プログラム種別について補足
修正プログラム種別について補足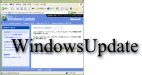 修正プログラム種別について補足
修正プログラム種別について補足
Microsoftのセキュリティ情報ページ
Windowsに関するセキュリティ情報がまとめられています。
ここから、セキュリティ情報の一覧を選択することで、修正プログラムと、関連する情報を入手することができます。
※この内、セキュリティ対策や不具合の修正に効果が期待できるものは、”重要な更新とServicePack”に含まれます。
通常の利用であれば、WindowsUpdateの機能を利用した方がよいでしょう。
サーバやシステムの管理者は、定期的に参照してください。
セキュリティホールやシステムの不具合が発覚すると、MicrosSoft社は、
まず、問題毎に修正プログラム(パッチ)を開発し、公開します。(その頻度は一週間に一つ以上。)
※一週間に一度以上の頻度で公開されていることから、週刊とも呼ばれています。
ネイティブなWindows環境(英語版)に対応するものが、最も開発が早く、
自社内にける動作確認を経て、重大な問題が確認されなければ、即時公開されます。
この時点では、公開テストは行われておらず、パッチとしての安全性は非常に低いものになります。
※英語版用の個別修正プログラム(パッチ)が最も早期に公開されます。
但し、日本語環境における動作は保証されず、かつ、安全性に問題があります。
(各システム管理者は、緊急を要する場合、こちらを適用することも考慮する必要があります。
セキュリティホールに対する、新種ネットワークウイルスの発生が懸念されるなど)
更に、この内容は各国のMicrosoftの開発室に渡され、各国の環境下に適用する形にカスタマイズされます。
各管理者は、自己の環境を見直し、適用するかの判断行う必要があります。
※日本語用の個別修正プログラムは数日間のタイムラグの後、公開されます。
この場合も、テストは自社内で行われているのみであり、自分の使用している環境における影響力は未知数です。
問題の波及範囲と、自己の環境を慎重に見極めて適用して下さい。
他の手法で、一時的にでも問題が回避可能であれば、適用後の修正プログラムに対する評価が得られる、
もしくは安定版がリリースされるまで状況を見守った方がよいでしょう。
また、各修正プログラムの適用時に、バックアップをするように明示的に指定することで、
適用前の環境に戻すことが可能です。
改訂版の公開や、不具合の発生に対応するため、
個々の修正プログラム毎に、環境のバックアップ(修正プログラム適用時に実行可能)と、
データのバックアップを取っておくようにしましょう。
※修正プログラムは一般に公開後、多くの場合、改訂が行われます。
様々な環境下における運用情報と、フィードバックが得られるためです。
個別の修正パッチを適用する場合は、必ず必要なものだけを、公開された順番に適用していきましょう。
※テスト環境になるべく近い形で適用することで、問題の発生率を下げ、
また、同一環境下にける、他者のドキュメントや、トラブルの情報を参考にすることができます。
※修正プログラムにも依存関係が存在することがあり、別の不具合を誘発させることがあります。
個別の修正プログラムは、公開→フィードバック→改訂→公開 のライフサイクルで、動作が安定したものになっていきます。
WindowsUpdateに表示される場合、多くは安定版か、緊急性が高いものです。
必要な措置を取った後、必ずインストールしてください。
累積パッチ
個別の修正プログラムは、関連する問題毎に纏められ、累積パッチとして提供されます。
※主にWindowsUpdateにて、目にすることになります。
あくまでも、関連する修正パッチの集合体に過ぎないため、問題点はそのまま残っています。
(改訂が行われている可能性がある分だけ、信用できるのですが……)
Windows○○(OSのバージョン名)
WindowsUpdateに表示される場合、多くは安定版か、緊急性が高いものです。
必要な措置を取った後、必ずインストールしてください。
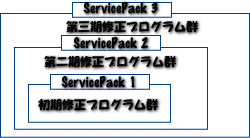 ServicePackは、特定のフェーズまでに発行された修正プログラムと、システム面の改修を一つの修正モジュール(プログラム)に
ServicePackは、特定のフェーズまでに発行された修正プログラムと、システム面の改修を一つの修正モジュール(プログラム)に
したものです。
(ServicePack2は、ServicePack1の内容と、差分にあたる新しい個別修正によって構成されます。
更に、ServicePack3はそれらを含みます)
全ての修正プログラムが収録されているわけではありませんが、
『ServicePack + 他にWindowsUpdateに収録されている修正プログラム』を適用することで、
多くの脅威から身を守ることができます。
一般に公開する前に、十分な公開テストが実施されているため、
個別に(webページから直接)修正プログラムをダウンロード、実行するよりも安全、かつ、効率的です。
但し、環境が大きく変更されることにもなり、使用しているのコンピュータ(周辺機器)や、ソフトウェアによっては、
致命的な不具合を招くことがあります。
通常のコンピュータであれば、不要な周辺機器を除去し、
ノートパソコンであれば、製造元のサイトより、対策方法やプログラムを入手した上でアップデートを行ってください。